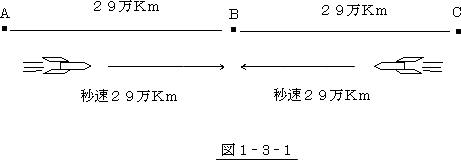
�i�O�j�@�����x�s�ς̌����ɍ����͖���
�@
�@�A�C���V���^�C���͌����x�͐�ŁA�����Ȃ���̂����������Ȃ��Ƃ��܂����B
�@����͖{���ɐ������̂ł��傤���B
�@����ׂ邽�߂ɁA�F����ԂɁ@A�AB�AC�@�Ƃ����O�̒n�_��ݒ肵�܂��傤�B
�@A �� B �̋����� 29��km ����AB �� C �̋����� 29��km ����Ƃ��܂��B
�@A�AB�AC �̎O�̒n�_�͒�����ɕ���ł��܂��B
�@A ���烍�P�b�g��b�� 29��km �̑����ŁAB �̕����Ɍ����Ĕ��˂��A�������� C ��������P�b�g
��b�� 29��km �̑����ŁAB �̕����Ɍ����Ĕ��˂����Ƃ��܂��傤�B
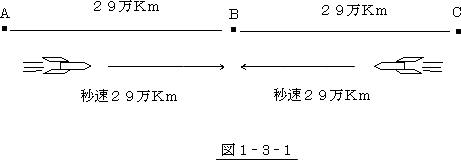
�@���̓�̃��P�b�g�͈�b��ɂ� B �n�_�ŏo��܂��B
�@���ʂ̊��o�Ō����A���̓�̃��P�b�g�̑��Α��x�� �b�� �T�W���j�� �̂͂��ł��B
�Ƃ��낪�A�A�C���V���^�C���́A��̃��P�b�g�̑��Α��x�� �b�� �R�O���j�� ���Ȃ���
���܂����B�@������A�����Ȃ邩��ł��B
�@�ł��A���̎��̌��ʂ́A�����ɍ����܂���B
�@���Θ_�ł́A�ǂ��炪�����Ă��邩�́A���ΓI�Ȃ͂��ł��B
�@A �̃��P�b�g����܂��Ă��āAB �n�_�� C ���P�b�g���AA ���P�b�g�̏��ɁA����ė����Ɖ���
���Ă������킯�ł��B
�@�����ŁA�������߂�����A�ǂ��Ȃ�ł��傤���B
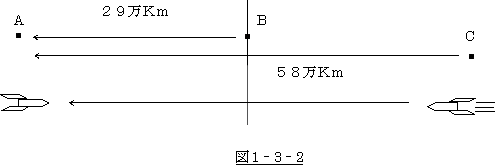
�@B �n�_�́A�P�b�Ԃ� 29��km �̋������ړ����āAA ���P�b�g�̂Ƃ���ɂ���Ă��܂��B
�܂�b�� 29��km �̑����ňړ����ė������ƂɂȂ�킯�ł��B
����͖�肠��܂���B
���ɁAC �̃��P�b�g��
29 �{ 29 �� 58��km
�̋����� �P�b�Ԃ� A ���P�b�g�̂Ƃ���܂ł���Ă������ɂȂ�܂��B
�@���ꂪ�A�b�� 58��km �łȂ��ĉ��ł��傤���B
�P�b�Ł@58��km �̍����k�߂����A������b�� 58��km �ł��傤�B
�@���Θ_�̗����͓��������Ă��܂��B
�@�����ŁA���ꂩ�炱�̖��̌����ɂ��ĉ𖾂��Ă������ɂ��܂��B
���A���̑O�ɁA�����������A��{�I�Ȃ��Ƃ��炠�����Ă����܂��傤�B
�@�@�A�C���V���^�C���̏o�������ΐ����_�̍����́g�����x�s�ς̌����h�ɂ���܂��B
�@�ł́A���́g�����x�s�ς̌����h�͈�̂ǂ����琶�܂ꂽ�̂ł��傤���B
�@����́A�}�C�P���\���E���[���[�̎�������ł��B
�@�}�C�P���\���ƃ��[���[�̓�l�́A����`����}�̂Ƃ��ẴG�[�e�������݂���̂��ǂ�����
���ׂ�ׂɎ��������܂����B
�@�F���ɃG�[�e�����[�����Ă���̂Ȃ�A�n���̓G�[�e���̊C�̒����j������Ă���悤�Ȃ��̂ł��B
�����A�����ł���Ȃ�A�G�[�e���͒n���̓����Ɣ��̕����ɗ���Ă��鎖�ɂȂ�܂��B
�@�����ŁA�ނ�͍l���܂����B
�@�G�[�e���̗���ƕ��s�Ɍ��������������ꍇ�ƁA���p�ɉ����������ꍇ�Ƃł́A���̑��s���Ԃ�
�Ⴄ�̂ł͂Ȃ����A�ƁB
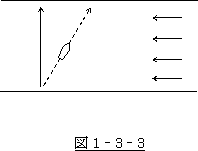
�@����́A�M���ɓn���ꍇ�̗�������ސ�����܂��B
�@�M���̑Ί݂ɓn���ꍇ�A�M�͗���ɗ�����܂��̂ŁA���炩����
�㗬�Ɍ����Ď߂ɐi�܂Ȃ���Ȃ�܂���B
�@��������ƁA���̏ꍇ�A�M�͎��ۂ̒����������������q�s���鎖��
�Ȃ�܂��B
�@�@�����Ƃ��A�ڊ݂̂��߂ɑD���݂ɕ��s�ɕt����ꍇ�́A�q�s���@��
�����قȂ�܂����A����́A�P���������c�_�ł�����A�ׂ������͖��Ȃ��ł��������B
�@�܂��A��ɕ��s�ɐi�ޏꍇ�ł��A�㗬�Ɍ����ꍇ�Ɖ����Ɍ����ꍇ�Ƃł͏��v���Ԃ�����ė��܂��B
�@�㗬�Ɍ����ꍇ�A�M�͗���ɂ���Č�������܂��̂ŁA�������Ԃ͒x��܂����A�A��͉��������
�Z�����ԂŒ����Ă��܂��܂��B
�@���̗l�ɗ���ɕ��s�ɐi�ޏꍇ�ł��A���Ɖ���Ƃł͍q�s���Ԃ��Ⴄ�̂ł��B
�@���l�̎������ɂ��Ă������锤�ł��B
�@�����A�G�[�e�������݂���̂Ȃ�A��̌����A�G�[�e���̗���ƒ��p�ȕ����ƕ��s�ȕ����Ƃ�
�����ē������������������ꍇ�A���͓����ɂ͖߂��ė��Ȃ��ƍl�����܂��B
�@�����Ŕނ�́A�}1-3-4 �̗l�Ȏ������u���l�Ă��܂����B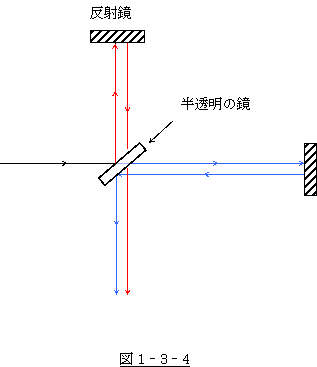
�@���̑��u�Ɍ���ʂ��A�G�[�e���̗�������s�ȕ���
�����p�ȕ����Ƃɕ����ē������������������Ȃ�A
�����A���̌��́A�����ɂ͖߂��ė��Ȃ��ł��傤����A
�����ɂ́A�����Ɗ��Ȃ��o�邾�낤�ƁB
�@�G�[�e���̗���̐��m�ȕ����͔�(�킩)��Ȃ��Ă��A
���̑��u����]��̏�ɏ悹�ĉA�K�Ȉʒu��
�������A���Ȃ��o�锤���ƁB
�����l���Ď��������̂ł����A���ǁA���Ȃ͏o��
����ł����B
�@���̎������ʂ����āA�A�C���V���^�C����
�s �����Ă���n���猩�Ă��A�Î~���Ă���n���猩�Ă�
���̑��x�͓��� �t�Ə���Ɍ��߂����̂ł��B
�@�������A����́A�]��ɂ����v�ł����B
�@���̎����Ŕ�(�킩)�������́A�u����܂ōl�����Ă����l�ȃ^�C�v�́A���̔}�̂Ƃ��ẴG�[�e����
���݂��Ȃ��v�Ƃ����������������̂ł��B
�@����ȏ�ł��Ȃ���A����ȉ��ł�����܂���B
�@���̓������A���̔������̌n�̉^���ɕt�����Ă����ƍl����A���̎������ʂ͉��ł��Ȃ��Ȃ�܂��B
�@���ꊵ���n�ŁA�������Î~�n�������ł̎����ł�����B
�@�n���ゾ���Ŋώ@�������A�������k�Ɍ��˂����Ă����ʂł��傤�B����́A����A���
�̒����i�s�����ƁA���̐i�s�����ƒ��p�ȕ����ƂɌ��˂����Ē��ׂĂ݂�l�ȕ�������ł��B
�@����ł͈Ӗ�����܂���B
�@�{���ɒ��ׂ�������n���̊O����ώ@���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�������Ȃ���g��Ԃ̊O���猩����h�Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B
�@�ނ���n���̊O����ώ@���܂������H�@����Ă��Ȃ��ł��傤�B
�@�ɂ��ւ�炸�g��Ԃ̊O���猩����h�ƁA����Ă���̂����Θ_�Ȃ̂ł��B
�@�g�����x�s�ς̌����h�ɍ����ȂǗL��܂����B�N���������Ă��Ȃ��̂ł�����B
�@����́A�A�C���V���^�C���̑����_���琶�܂ꂽ���ł��B
�@���Ɂg���̎������{���ɐ������Ă���̂��ǂ����h�Ƃ����������ɂȂ�܂��B�ƌ����̂́A�}�C
�P���\���ƃ��[���[�̓�l�͒n���̉^�������]�ōl���Ă�������ł��B
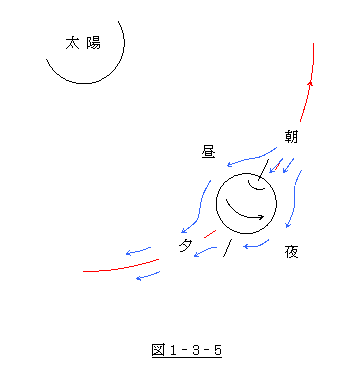
�u���]�ʼn��������I�v�ƌ���ꂻ���ł����A���́A
���]�ɂ͖�肪�L��̂ł��B����͎��]�Ƃ̂����
����ł��B
�@���]�ōl����A�G�[�e���͓����琼�֗����
�����ł����A���]�ł͂����͍s���܂���B
�@���]�̏ꍇ�G�[�e���̗���́A���E���E�[�E���
�ς���ė��܂��B
�@��͓����琼�ւƗ���A���͐����瓌�ւƗ����
�����܂��B�����āA�����ɂ͓��ォ��~�蒍���A
�[���ɂ͓V��ւƏ����čs���܂��B
�@���̗l�ɗ��ꂪ�ϓ]���Ē�܂�Ȃ��̂ł��B
�@��]����g���Ă���̂�����A�����A�������ς���Ă��Ή��o�������ȋC�����Ȃ��ł�����܂���
���A���͂����ȒP�ł͗L��܂���B
�@�w���㕨���̐��E�]�T ���ΐ����_�Ɨʎq�͊w�̒a���x
�u�k���@151�łɂ��܂��ƁA���_���o����
�u�Ō�̎�����1887�N�̂W���̂W,�X,10,11���y��12���̒��Ɨ[���ɍs��ꂽ�v�Ƃ���܂��B
�@�����Ŗ��Ȃ̂́A���Ɨ[���ł��B
�@���]�ł́A�G�[�e���͒����ɂ͓��ォ��~�蒍���A�[���ɂ͎l������W�܂��ēV��ɏ����čs����
���B����ł́A��]����ǂ����ɉĂ����ʂł��傤�B
�@�B��̉\���́A���]�ɂ��G�[�e���̗��ꂾ���ł��B
�@�u�����̌��ʂ́A���]�ɂ��G�[�e���̗�������ے肵�����ɂȂ�̂�����A�ʂɖ�薳���ł͂�
�����B�v�ƌ���ꂻ���ł����A�������s���܂���B
�@�n���̓����͎��]�ƌ��]�����ł͂Ȃ�����ł��B
�@���z�n���̕����A�����Ă���̂ł�����A���̉e���ɂ��G�[�e���̗�������������Ȃ���Ȃ�
�܂���B
�@���z�n�͕b�� 20�����ŋ߂��̍P���n������Ă��܂��B�����āA���̍P���n���b�� 320�����ŋ�
�͌n�̒����Ă��܂��B���̎��ɁA���̋�͌n���܂��b�� 160�����ő��̋�͌n�ɑ��ē����Ă���
�̂ł��B
�@(�w���Θ_�͂����ɂ��Ă���ꂽ���@�A�C���V���^�C���̐��E�x�u�k��(BLUE BACKS) 64�� �Q�� )
�@��������ƁA�G�[�e���̗���ƌ����Ă��A�{���̏��A�ǂ����̕������痬��Ă���̂��A��������
���������Ȃ��Ȃ�܂��B���G����ȗ���ƂȂ锤�ł��B
�@�n���̎��]�ɂ��G�[�e���̗�����A���̉^���̗���ɂ���đ��E(��������)����Ă��Ȃ��Ƃ�����
��܂���B
�@�Î~���Ă���G�[�e���̒���n�����j������Ă���Ɖ��肷��̂Ȃ�A�F���̂ǂ�������ΓI��
�Î~���Ă���_�������o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł��B�����āA��������_�Ƃ��āA�n���̉^����
����������o���Ȃ���Ȃ�܂���B
�@�������Ȃ���A�G�[�e���̖{���̗���͂��߂Ȃ��ł��傤�B
�@����������͕s�\�Ȏ��ł��B
�@�������́A��ΐÎ~�_��F�߂鎖�ɂȂ�A���ΐ��̌��������ے肷�鎖���Ȃ�܂��B
�@����́A���A���Θ_�����ے肷�鎖�ɂȂ��������
�@����Ȏ��͑��Θ_�M��҂ɂ͐�ɔF�߂��Ȃ����ł��傤�B
�@�]���āA���̎������ʂ����Đ������Ă���̂��ǂ����A���Ƃ������Ȃ��Ȃ�܂��B
�@�����������ł�����A���̎������ʂ���u�����x�s�ς̌����v�f����ȂǁA�����Ă̊O�Ȃ̂ł��B
�@�u�����x�s�ς̌����v�ɍ����ȂǗL��܂���B
�@����̓A�C���V���^�C���̋�z��萶�܂ꂽ���ł�����B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����@�@�@�@�@�@�@�ł̓��ɖ߂��@�@�@�@�@�@�@�O�̕łɖ߂��@�@�@�@�@�@HOME�ɖ߂�