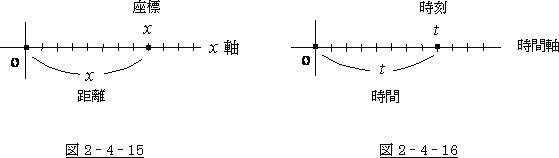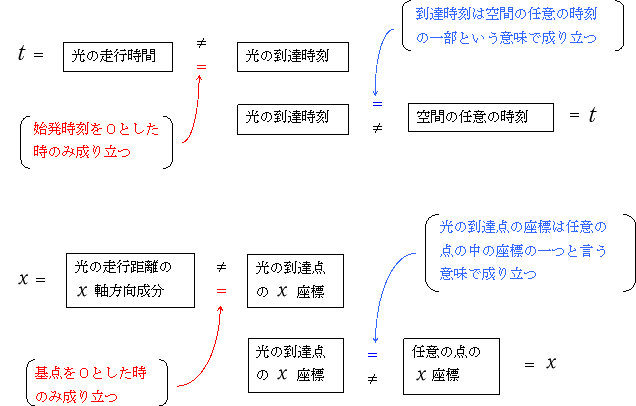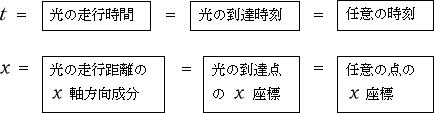(三) 各論の誤りのまとめ
今までの論証で明らかな様に「同時性」「ローレンツ収縮」「時間の遅れ」等の説は全て間違っています。
これらの説には何の根拠も有りません。
そして、その間違いの元はローレンツ変換の使用に有ったのです。
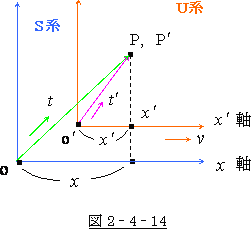 アインシュタインは、ローレンツ変換を任意の座標や任意の時刻
アインシュタインは、ローレンツ変換を任意の座標や任意の時刻
の変換公式と思い込んで使用しました。
これがそもそもの間違いの元でした。
ローレンツ変換は 図2‐4‐14 に於ける光の走行距離と走行
時間の関係式だったのです。
決して任意の座標や任意の時刻などの変換式では有りません。
では、どうして、この様な間違いを生じたのでしょうか。
それはアインシュタインが「距離」と「座標」,「時間」と「時刻」とを混同していたからです。
ここで、「距離」と「座標」の違いについて説明しておきましょう。
「座標」とは 特定の点の位置であり、
「距離」とは ある座標から別の座標までの間の長さです。
そして、「時刻」とは 時間軸上の特定の位置であり、
「時間」とは ある時刻から別の時刻までの間の長さ
です。アインシュインはこれらに区別をつけず混同していました。
その為、後から追随される先生方も気づかず混同されたのでしょう。
ではなぜ混同してしまったのかというと、それは文字と用法に原因が有ります。
文字で書けば、距離も座標も同じ  の文字で表されます。
の文字で表されます。
そして0を基点にすれば、距離は座標の数値で代用されます。だから混同をしてしまうわけです。
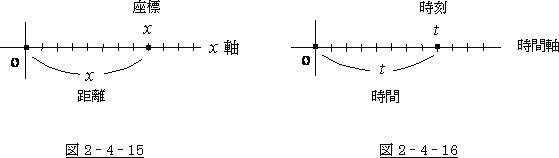
次に、時刻と時間も同じ  の文字で表わされます。
の文字で表わされます。
そして 0 を始点とすれば、時間は時刻の数値で代用されます。従って混同はされます。
その上、もっと始末の悪い事に「時間」という言葉は「時刻」と「経過時間」の両方の意味を兼ね
備えています。
これは日本語だけでなく英語の time でもドイツ語の Stunde でも同じようです。
本来、人は、その時々に応じて使い別けているのですが、どうもアインシュタインは論文を書く時、
気づかず混同してしまった様です。
その結果、本来、光の走行時間である  が光の到達時刻に置き換えられ(ここまでは良いのですが)、
が光の到達時刻に置き換えられ(ここまでは良いのですが)、
それが空間の任意の時刻にまで拡大解釈されてしまったのです。
次に、光の走った距離 OPの  軸方向成分である
軸方向成分である  も、光の到達点(P点)の
も、光の到達点(P点)の  座標と解釈される所
座標と解釈される所
までは良いのですが、これが、任意の点の  座標と拡大解釈されてしまう所に問題があるわけです。
座標と拡大解釈されてしまう所に問題があるわけです。
本当は
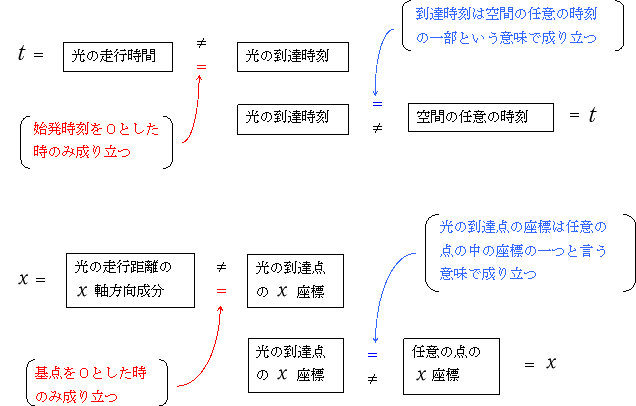
だったのです。
それぞれの項目は、皆、別の物ですが隣接する項目に特定の条件をつければ = が成立します。
だからと言って離れた項目まで = になるわけではありません。
そこの所の区別・たて別けに気づかず三段論法でやると
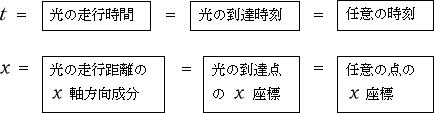
とやってしまい、間違いを生じてしまいます。
似た物をくっつけて、安易に、同じとしてしまうのは問題でしょう。
というわけで、ローレンツ変換と教科書の設定とは何の関係もありません。
設定と式とが無関係ですから。
この様な設定にローレンツ変換を使おうというのは、バスの燃費を計算する式でもって亀の寿命を
計算したり、体脂肪を計算する式でもって生徒の偏差値を計算する様なものです。
その様な事をすれば滅茶苦茶になります。
しかして、その滅茶苦茶をやっているのが相対論というわけです。
従って、相対論は全くの誤りなのです。
と、ここまで申しますと専門家の先生方は、たぶん
「お前が指摘しているのは教科書の執筆者のミスであって、アインシュタインのミスではない。
アインシュタインはその様な導き方はしていない。だから、相対論が間違ってるとは言えない。」
と仰られるでしょう。
そこで、次は、アインシュタインの論文について論評することにします。
次へ 頁の頭に戻る 前頁に戻る HOMEに戻る
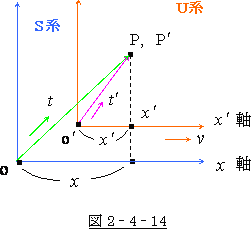 アインシュタインは、ローレンツ変換を任意の座標や任意の時刻
アインシュタインは、ローレンツ変換を任意の座標や任意の時刻